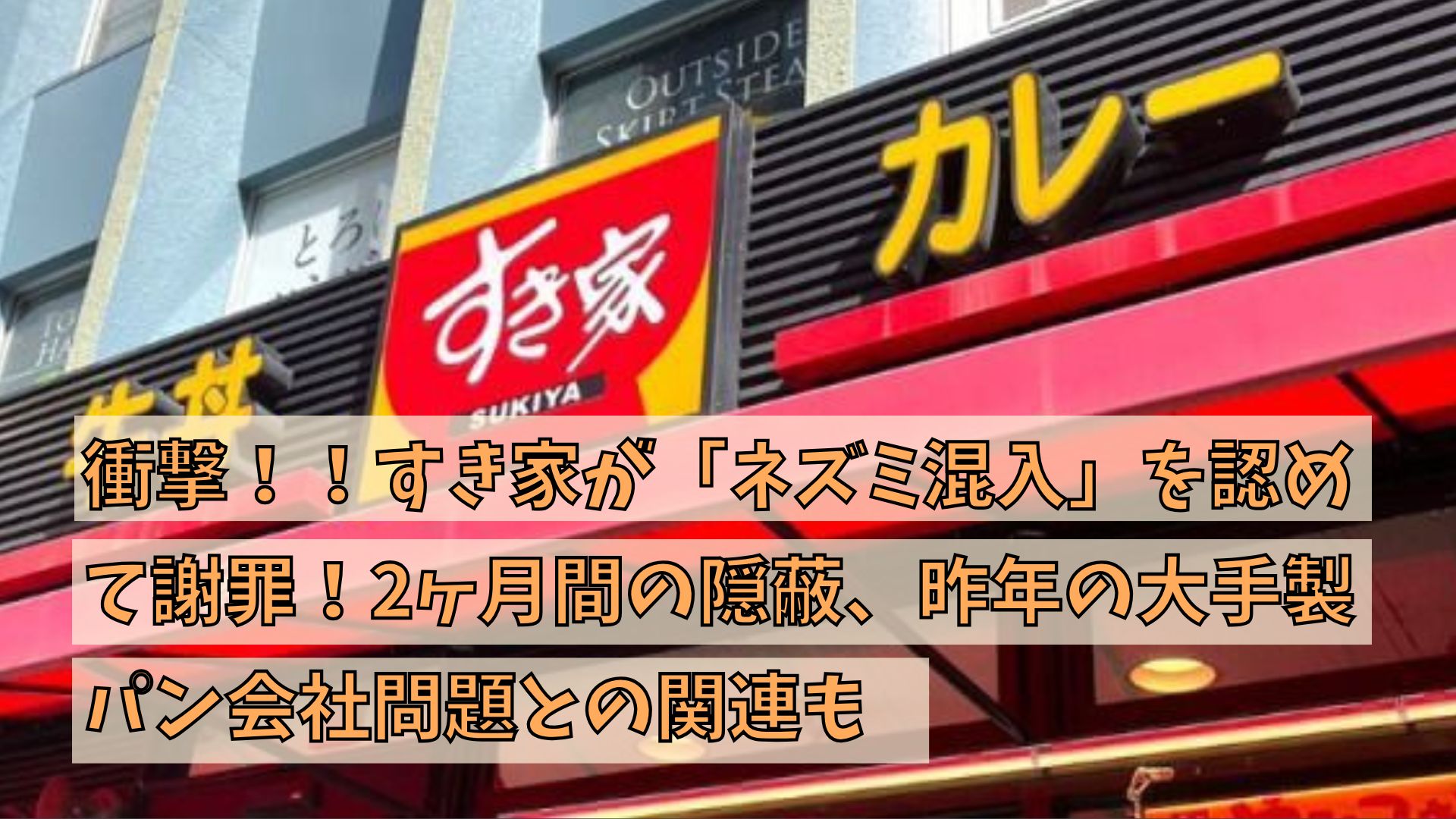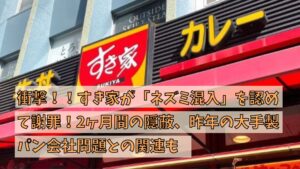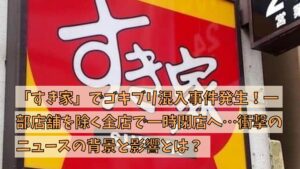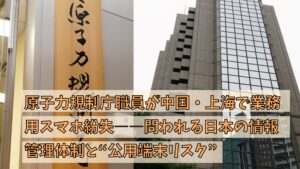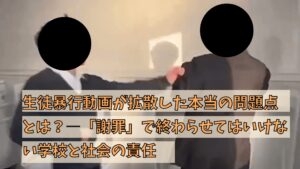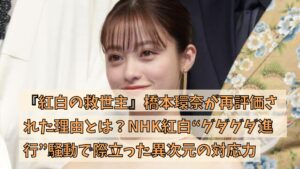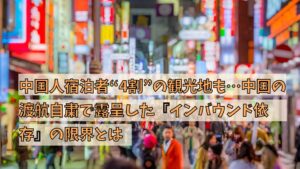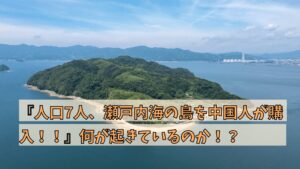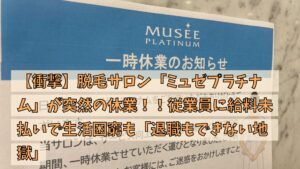2025年3月、牛丼チェーン店「すき家」において、驚くべき事態が発生しました。すき家で提供された味噌汁の中に、なんと「ネズミの死骸」が混入していたことが報じられました。この事件は、瞬く間にSNSやニュースで拡散され、消費者の間に大きな衝撃を与えました。
事件が発覚したのは、あるお客さんがすき家で食事を楽しんでいた際、味噌汁の中に異物を発見したことから。驚きと共に、その異物が「ネズミの死骸」であることが判明し、すき家の店舗に連絡が入った。この時点で、店舗側はすぐに対応し、問題の商品を回収、その後の調査で、店舗内で不適切な管理が行われていたことが明らかになりました。
すき家の謝罪と原因の説明
すき家は、問題が公になるとすぐに公式声明を発表。事件を受けて謝罪し、「従業員が提供前に商品の目視確認を怠ったことが原因で、ネズミの死骸が混入した」と説明した。
企業側によると、問題が発生した店舗では、食材の確認を徹底していたつもりだったが、今回の件で従業員が目視確認をしっかり行わなかったことが致命的だったと認めている。また、すき家は調査の結果、食材が納品された時点で既に異物が混入していた可能性もあると発表している。
すき家は謝罪の意を込めて、該当店舗の閉鎖、並びに従業員への再教育を行うことを約束。さらに、他の店舗にも品質管理の徹底を指示した。
隠蔽されていた約2ヶ月間の期間
衝撃的なのは、この問題が約2ヶ月間も公にされず、隠蔽されていたという事実だ。事件は2025年1月に発生していたが、その後、すき家は約2ヶ月間、何も発表せず、消費者に対して一切の報告を行わなかった。この期間中、問題のあった店舗での営業は続けられ、他の客にも同じような問題が発生していた可能性がある。
隠蔽されたことが明るみに出ると、消費者の怒りはさらに高まった。SNSでは「隠蔽するなんて信じられない」「消費者を裏切った」といった声が続出。すき家の対応には批判の声が多く、企業の透明性が問われる結果となった。
昨年の大手製パン会社での類似事件
すき家の「ネズミ混入」問題は、決して単独の事例ではない。実は、昨年にも類似の問題が発生しており、注目すべきは「大手製パン会社」による事件だ。この大手製パン会社では、工場内で製造されていたパンに「ネズミの死骸」が混入していたことが発覚。これも大きな騒動となり、消費者の間で信頼の問題が浮き彫りになった。
食品業界全体において、こうした「異物混入事件」は珍しいことではない。しかし、これらの事件は企業の対応が不十分だったり、隠蔽されていたりすることが多く、消費者からの信頼を大きく損なう原因となる。
すき家の事件は、業界全体で品質管理や透明性が重要であることを再認識させるものであり、消費者の信頼回復に向けた改善が急務であると言えます。
消費者の信頼回復に向けて求められる対応
「ネズミ混入」というショッキングな事実が明るみに出た以上、すき家は消費者の信頼を回復するために積極的な対応が求められる。まず第一に、再発防止策の徹底が必要だ。企業が行うべき具体的な対策としては、以下のようなものが考えられる。
- 品質管理の徹底:全店舗における衛生管理や食材の確認作業の強化。
- 従業員教育の徹底:特に店舗での目視確認や衛生管理について、従業員に対する再教育を行うこと。
- 透明性の確保:問題が発生した場合、隠蔽せず、速やかに消費者に報告する体制を整える。
- 第三者機関の監査:外部の監査機関による定期的な検査を受け、信頼性を高める。
また、企業側は謝罪だけでなく、消費者の不安を払拭するための具体的な行動を示さなければならない。信頼回復には時間がかかるかもしれないが、誠実な対応が最も重要だ。
まとめ
「ネズミ混入」事件をきっかけに、消費者の食品に対する意識が一層高まることは間違いないでしょう。今後、食品業界は品質管理の強化、衛生管理の徹底、透明性の向上が求められるでしょう。消費者側も、より慎重に商品を選ぶようになり、企業に対してより高い基準を求めることが予想されます。
すき家の今回の事件は、一企業の不祥事にとどまらず、食品業界全体に対する警鐘となったと言えます。今後、業界全体がどのように改善し、信頼を取り戻すかが大きな課題となります。